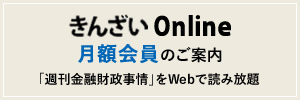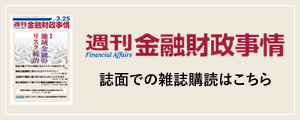アクセンチュア ビジネスコンサルティング本部 /信森 毅博
連載セミナーゼロから学ぶコンダクトリスク 第1回
Web限定
近年、「コンダクトリスク」への関心が高まっている。コンダクトリスクとは非財務リスクの一つで、企業の役職員の行為(conduct=コンダクト)が外部ステークホルダーに不利益をもたらし、企業価値を低下させるリスクを指す。金融業界での著名な例としてLIBOR不正操作が挙げられる。そのほかにも、データ・情報の不適切な扱いや金融商品の販売方法など、顧客に不利益をもたらすさまざまな行為がコンダクトリスクとされる。
関心が高まっているのは、長く許容されてきたビジネス上の対応を巡って、しばしば社会的に問題となるケースが増えているためだろう。問題に巻き込まれた当事者からは、「業界慣行や社内ルールを守ってきた中で、後から非難されても納得がいかない」との本音も聞かれる。そうした気持ちは分からなくもない一方で、コンダクトリスクが業界や自社の「常識外れ」に内在している点が踏まえられていないようにも感じる。
本連載ではコンダクトリスクについてさまざまな具体例を踏まえ、筆者の考えを整理したい。

のぶもり たけひろ
東京大学法学部卒、91年日本銀行入行。11年からコンサルティング会社にて内部統制やコンプライアンス等の態勢整備を支援。20年から金融庁でコンダクト企画室長として顧客本位の業務運営のモニタリング等に従事。23年から現職。

掲載号 /週刊金融財政事情